
身近であえる生き物たち
チャンネル登録者数 648人
557 回視聴 ・ 6いいね ・ 2025/07/01
ゴマダラカミキリ
和名:ゴマダラカミキリ
学名:Anoplophora malasiaca
分類:節足動物門>昆虫綱>有翅昆虫亜綱>甲虫目>カブトムシ亜目>カミキリムシ科>フトカミキリ亜科
分布:北海道・本州・四国・九州・沖縄
大きさ:25-35mm
時期:6-8月
食料:木の葉や樹皮
越冬態:幼虫
生息:樹林、林縁
ゴマダラカミキリ
胡麻斑髪切
学名:Anoplophora malasiaca
コウチュウ目(鞘翅目)、カミキリムシ科に分類される甲虫の一種。
大型で姿が目立ち、また食樹も広範である為都市部の街路樹、庭木、公園樹木でもよくみられる。その為国産カミキリムシ中で最もよく知られる種の一つである。
和名は艶のある深い黒の体に白いゴマ柄に由来する。オスとメスはほぼ同型。一般にメスはオスよりやや大型で、オスの触角はメスよりはるかに長い。
生息環境は樹上性。里山、二次林など広葉樹を中心とする各種樹林とその林縁、公園、社寺境内、果樹園、桑畑、人家の庭などで見られる。幼虫は潜材性。
発生は年1回。6月~8月に見られる。越冬態は幼虫(非休眠)で、材内で摂食しながら冬を越す。
昼行性。夜間燈火に飛来することも少なくない。飛翔は緩やかで、活動はあまり活発でない。捕まえると胸部をこすり合わせてキイキイと音を出す。
幼虫の食性は材(生木)。クワ科のヤマグワ、イチジク、ヤナギ科ヤナギ類、ミカン科ミカン類などを好む。主幹に穿孔する。
成虫の食性は葉や樹皮(若枝)。主にクワ科のヤマグワ、イチジク、ヤナギ科ヤナギ類、ミカン科ミカン類など。ほかにバラ科のモモやバラ類などが知られる。
成虫の天敵はムシヒキアブ類、カマキリ類のほか、造網性クモ類。幼虫は捕食性コメツキムシ類の幼虫、ヒラタムシ類など。
交尾を終えたメスは生木の樹皮を大顎で傷つけ、その箇所に産卵する。主に根元付近の樹皮もしくは根元から1~2mの高さの幹に産卵することも多い。
幼虫(テッポウムシ)は生木の材部を食害し成長する。幼虫は成長すると幹内部を降下し、主として根株の内部を食い荒らす。
孵化から羽化までには1年~2年を要する。幼虫が侵入した樹木は幼虫の活動によって坑道が樹皮に達し穿孔され、木屑や樹液が出るようになる。
蛹を経て羽化した成虫は木の幹に円形の穴を穿孔し、野外に脱出する。時に産卵痕や脱出痕からは樹液が染み出すことがあり、昆虫が集まることもある。
幼虫が材部を掘り進むと直径10mm~20mmほどの坑道ができ、木の強度が弱くなって折れやすくなる他、成長不良に陥り、枯死することもある。
果樹や街路樹に被害が出ることもあり、特にミカン農家ではゴマダラカミキリは重大な害虫の一つとして警戒されている。
国内では北海道、本州、四国、九州の平地~山地まで分布。島嶼では奥尻島、佐渡、伊豆諸島、隠岐、対馬、壱岐、五島列島、種子島、屋久島、沖縄本島で記録。
国外では朝鮮半島、済州島、中国大陸、台湾、マレー半島に分布する。
◆撮影時期の定義
上旬:1日~10日
中旬:11日~20日
下旬:21日~月末
写真集(アマゾンで発売中)
身近であえる生き物たち
6月上旬
www.amazon.co.jp/dp/B0D37S8MZ9
3月上旬
www.amazon.co.jp/dp/B0F1JWNSG7
#昆虫 #虫 #生き物
埼玉県内特にさいたま市で発見できる生き物情報です。
地元埼玉で長年暮らしてきましたが、注意深く観察することで発見したことや
知っていた生き物の意外な一面などを発見して楽しんでいます。
基本的に採集は行っていません。
ほぼ触れる事もなく、生き物のありのままの状態を撮影しています。
コメント
関連動画
 8:25
8:25
【為にならないクワガタ紹介】インターメディアツヤ(ダールマンツヤクワガタ亜種インターメディア)編#Odontolabis intermedia dalmani
324 回視聴 - 3 週間前
使用したサーバー: direct
再生方法の変更
動画のデフォルトの再生方法を設定できます。埋め込みで見れるなら埋め込みで見た方が良いですよ。
現在の再生方法: 通常
コメントを取得中...




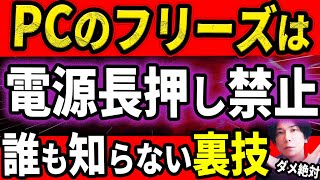


![6-②.【かっこいい】6月の野山で珍カミキリに出会う![昆虫探検1600『むしはかせへの道』]](/wkt/back/vi/Q7lyG8-kZXo/mqdefault.jpg)





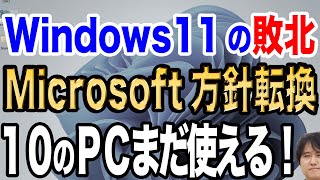
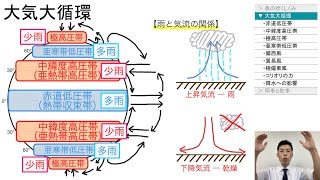









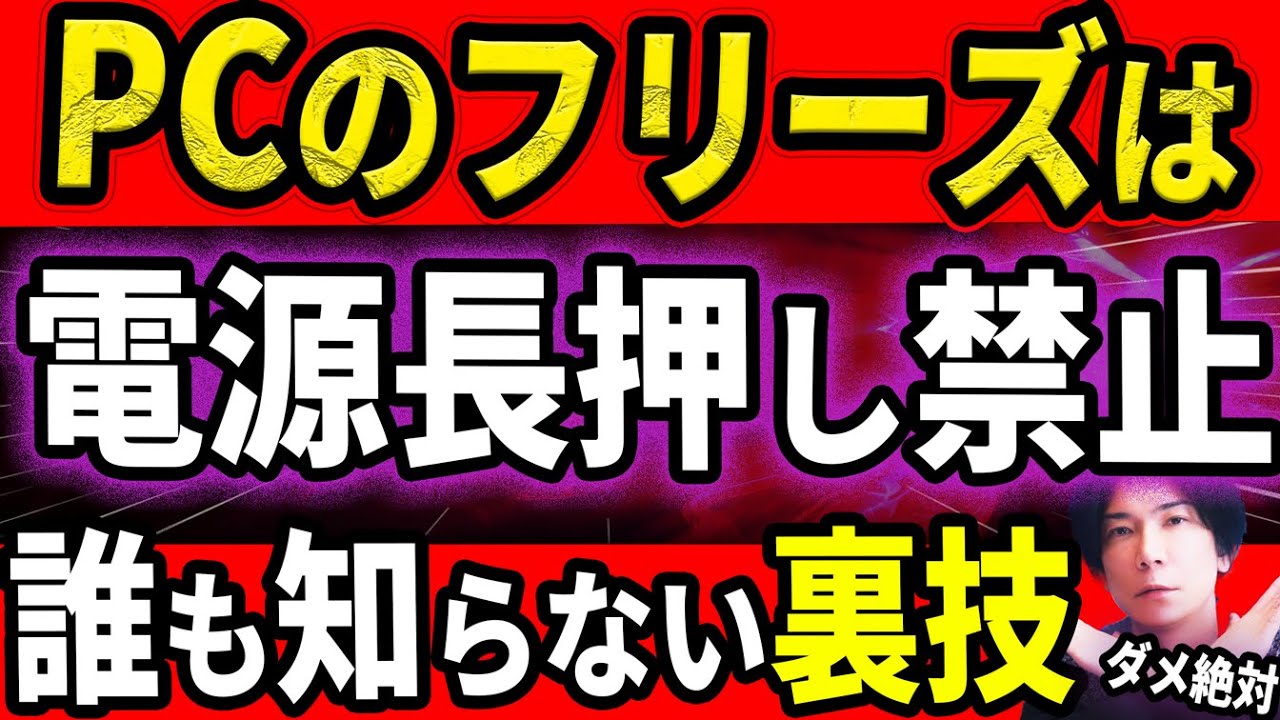








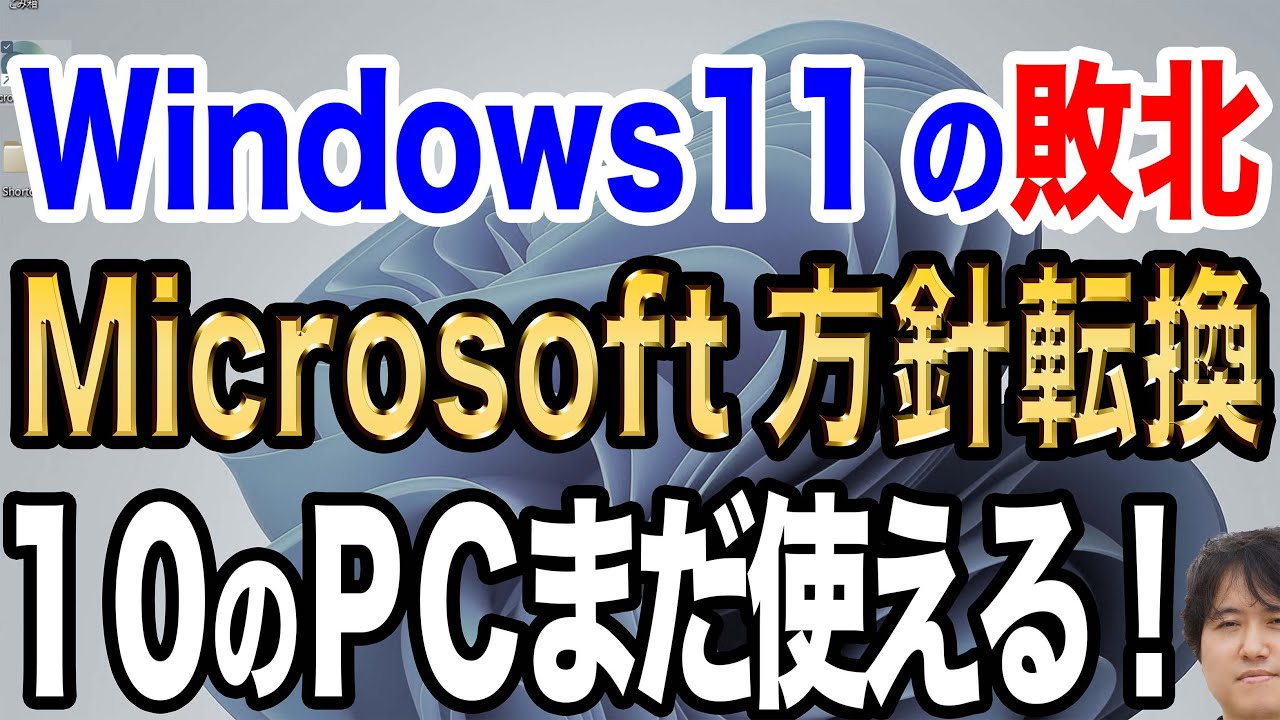
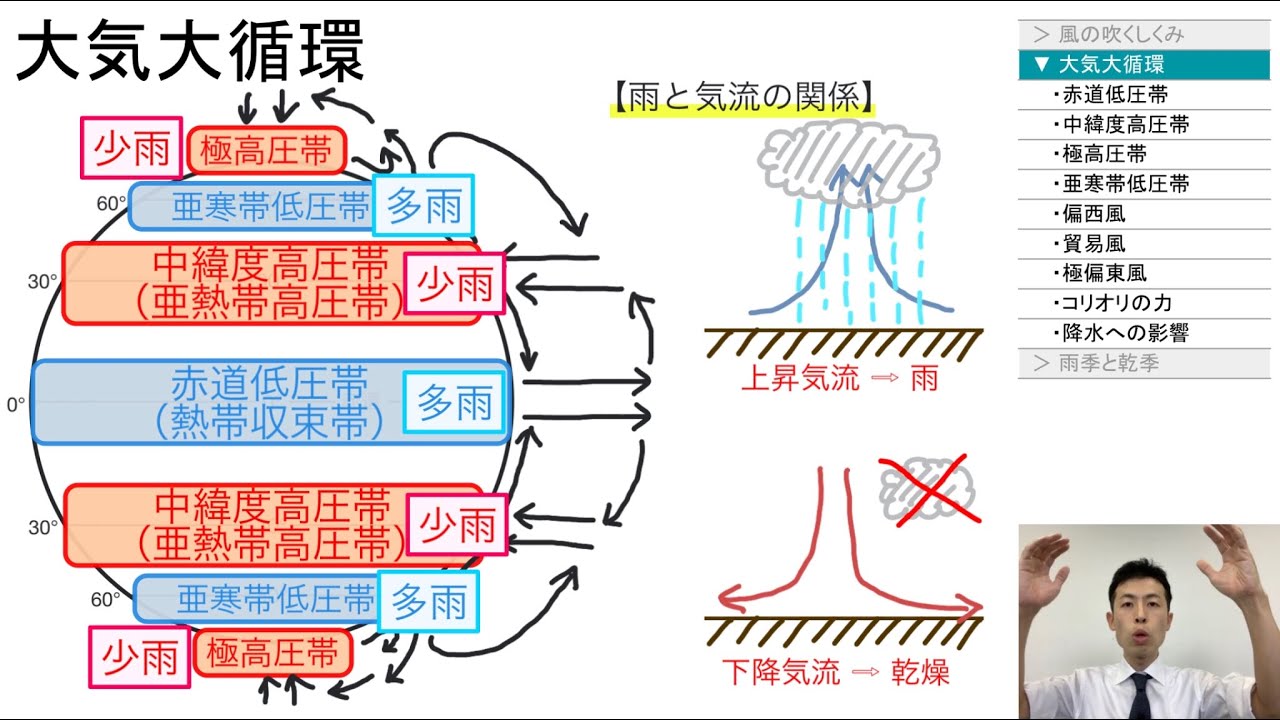




コメントを取得中...